船の雑学


船の雑学!」
こんにちは!キャプテンなみ丸だ!
みんなは普段、船のことをどれくらい意識しているかな?
何気なく見ている船だけど、よくよく考えると知らないこともたくさんあるよな!
今日は、そんな船にまつわる小さな発見や面白い話を紹介するぞ!
きっと船の世界が面白く見えてくるはずだ!


最初に船のちょっと意外な事実を教えよう!
実は船にはブレーキがついていないんだ。でも、当然だけど船は止まることができる。車や自転車のようなブレーキがない船がどうやって止まるのか気になるよな。
船は水面を滑るように進むから、タイヤのように摩擦で止まることが難しいんだ。
そのため船乗りたちは、潮の流れや風向きを見ながら計画的にスピードを落としていく。緊急の場合は、プロペラを逆回転させて減速するけど、実は巨大な船が完全に停止するまでには約3kmもの距離が必要なんだぞ。
では、逆に船が進む仕組みについても考えてみよう。この巨大な船を動かしているのが、エンジンなんだ。
実は、外航船のエンジンは超巨大で、なんと馬力が8万から10万もあるんだ。
エンジン自体も大きくて、長さ25m、高さ13m、幅6m、重さ約2300トンという、まるで一つの建物みたいなスケールなんだぞ。
さらに最近では環境を守るため、CO2排出を減らしたり、風力など自然エネルギーを利用した新技術の開発が進んでいる。
船は巨大で、地球にも優しい輸送手段なんだな!




そんな巨大な鉄の船がなぜ水に沈まないか考えたことあるか?
鉄は本来水よりずっと重いはずなのに。
実は船の中はほとんど空洞になっていて、全体の体積に対して水よりも軽い構造になっているんだ。
これが比重という原理で、船が水面に浮く秘密なんだぞ。それに船が波や風で転覆しないよう、船底や重心の位置を細かく計算して設計されているんだ。
仕組みだぞ!




次はちょっと視点を変えて、船に関わる名前の由来を探ってみよう。日本の船の名前に「丸」が多くつくことに気づいていたか?
これは平安時代の「マロ」(自分)という言葉から派生して敬愛の意味で使われたり、船を城に見立てて「丸」を付けたという説もあるんだ。
船名一つにも日本独特の歴史や文化が隠れているんだな。
込められているんだな!
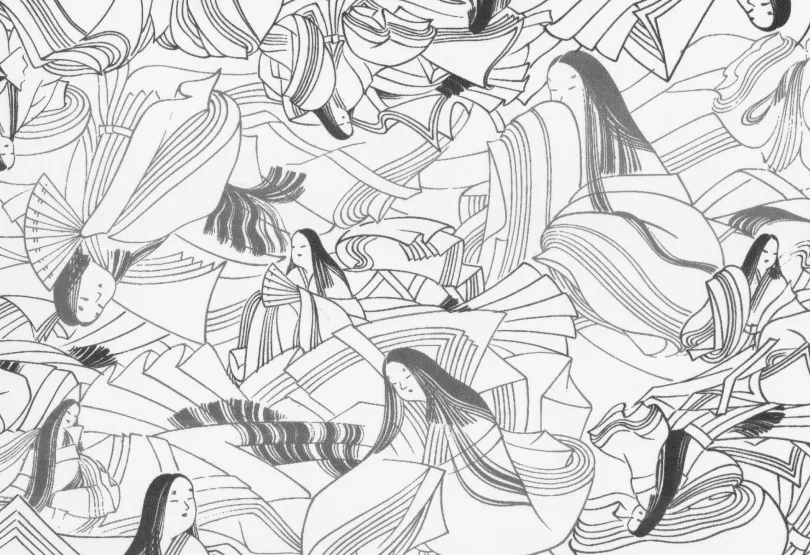



最後に、みんなの毎日の生活を支えている船の役割について触れてみよう。日本に入ってくる商品のほとんどが海上輸送によって運ばれているのを知っているか?
実際、日本の貿易量の約99.6%が船で運ばれているんだ。
船は一度に大量の荷物を安価に運べるから、食べ物や衣類、家電製品まで幅広く運ばれているんだぞ。航空輸送も便利だけど、一度に運べる量が少なくコストも高い。
だから日本経済、国民生活を維持するにあたって船が担う役割はとても大きいんだ!




船って身近な存在だけど、知れば知るほど面白いよね。
そんな船を動かしているのが「航海士」と「機関士」という人たちなんだ!
航海士は船の進む道を決めたり荷物の積み下ろしを指揮したりしていて、
機関士は大きなエンジンなど船内の全ての機器を点検・整備しているんだ。
『外航船員』という仕事は、こうした人たちが協力して船で世界中を巡る
素敵な仕事なんだ。
もし少しでも興味を持ったら、気軽に調べてみてくれよな!
いつか海で会えるのを楽しみにしてるぞ!


